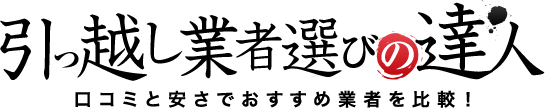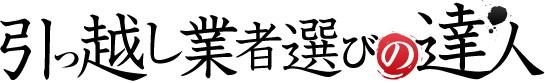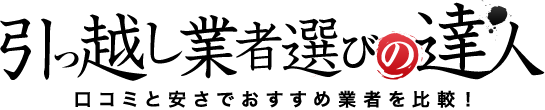新居の家具を適当に配置してしまうと、使いづらく住みにくい部屋になってしまいます。あとから自分で模様替えしようとすると、重たい家具で壁に傷をつけたり、腰を痛めたり、大変な目に遭いますよ。
だから、事前にレイアウトをよく考えて家具を配置することはとても大切です。
転居前にレイアウトを決めることの重要性
引「この洋服タンスはどこに置きますか?」
客「この壁に沿って、こう置いてください。」
引「そこだと押入れの引き出しケースが引き出せなくなりますよ。」
客「あ、じゃあこっちに。」
引「そうすると寝室なのにベッドが置けなくなりますよ。」
客「うっ。じゃあ、ベッドはとりあえず空いてるところに立てて置いてください。」
結局仕方なく押入れで寝たという笑うに笑えない話があります。同じ広さの部屋であっても、窓やドアの位置が違うなら今まで通りの配置にならないのは当然です。
大きく幅を取る家具や家電は窓やドア、コンセントやスイッチを塞がないような場所にしか置けません。となると、おのずと置ける場所の選択肢は狭まってくると思います。最低限、自分で動かすことのできない大きい家具や家電の位置だけでも、しっかりと決めておくべきです。
転居先の下見時にやるべきこと
下見に行く時には必ず巻き取り式のメジャーと、デジタルカメラやスマホを持って行くようにしましょう。裁縫用の短いメジャーではなく、金属製のロック機能のついている3m以上の金尺があれば色々な場面で重宝します。
間取り図を拡大コピーして書き込む
不動産屋から間取り図を手に入れ、大きめに拡大コピーして持参しましょう。そこに実際に測ったサイズをあとから見て分かるようにハッキリと手書きで書き込んでいきます。
これらの場所も書き込んでおきましょう。
- 天井の梁
- 天井の電気プラグの位置
- コンセントの位置
- 電気スイッチの位置
- テレビアンテナ端子の位置
- 電話端子の位置
- TVドアホンのモニター位置
- 給湯パネルの位置
- 窓のサイズ
- カーテンレールの長さ
- 腰高窓、出窓の高さ
- 柱の出っ張り
- 押入れの中段の高さ
- 防水パンのサイズ
- 水道蛇口の高さ
- 冷蔵庫置き場のサイズ
画像と動画に残すとイメージしやすい
間取り図に書き込んだら、次は収納スペースや壁や窓、梁など写真で残しておきましょう。収納場所の棚の位置なども重要になることがありますので、キッチンや洗面所の作り付けの収納扉やクローゼットや押し入れなどの扉を開いた時の写真も忘れずに。
部屋の中央に立って動画で360度のビデオ撮影をしておくと、立体的なイメージと部屋の空間の広さがわかりやすいのでおすすめです。
自宅の家具のサイズを測る
自宅の家具の幅と奥行きと高さを測っておきましょう。家電はインターネットでメーカーと品番を入力すると仕様のページでサイズを見ることができます。もちろん自分で測っても構いません。
扉や引き出しの可動範囲も
タンスなどの収納家具や食器棚は扉を開くのに横にある程度の空間を取らないと完全に開かないものか、可動範囲を確かめておきましょう。引き出しも、一番奥のものを取り出すのに必要な目一杯引き出したときの長さも記入しておくと良いでしょう。
椅子に座るのに必要なスペースも
ダイニングテーブルセットのイスから立ったり座ったりするときに必要なスペースもあらかじめ入れておきましょう。また、周りに家具を置いた時や椅子に座った時に後ろを人が通れるかどうか、その家具が支障なく使えるかも考慮する必要があります。
作り付けの収納場所に入れているものの行き先は
今住んでいる家の収納場所がたっぷりで、キッチンの収納棚の中にたくさんの調理器具や、お菓子作りの道具、調味料などのストック品、鍋やホットプレートやパン焼き器やジューサーミキサーなどあらゆるものを詰め込んでいる場合は、次の転居先にも同程度の収納スペースがあるかどうかが鍵になります。
入りきらないものはどうするのか、新たに収納スペースを増やすための家具を買うことになるか、今入れている物を処分することになるかもあらかじめ考えておくべきでしょう。
傷みや歪みを発見した家具は
自宅の家具のサイズを測っているときに、いろいろ気づくことがあります。板が真っ直ぐでなく歪んでいたり、なんとなくカビ臭かったり、弱くなった家具は、引っ越し中に何が起こるかわかりません。
トラックで長い間揺られ続け、ひどい状態のものは崩れてしまうことがあります。それ程までに使い倒した家具は引っ越し前に処分した方がいいですね。
実際にレイアウトしてみよう
まず、レイアウトを実際に決めるには、実際の間取り図を拡大コピーして、その上で厚紙をサイズ通りに切り抜いて作った家具を、あれやこれやと置き換えてみるのが一番確実で間違いがありません。
パソコンやスマホを使いこなせる人なら、無料ソフトやアプリの間取り図ソフトを使うのも便利です。ただし、ソフトの設定や使い方を把握するのに相当の時間を費やすようなら、早めに諦めて手書きで作った方が時間の節約になる場合もありますので、臨機応変にしましょう。
いよいよパズル感覚で家具の配置
ここからが本番です。実際の使い勝手や人の動線を考えながら、この位置以外にはない!と自信を持って言えるような配置が決まるといいですね。
定位置の決まっているものから
洗濯機や冷蔵庫は位置がすぐ決まりますね。とりあえずは、その部屋に置くべきもの家具のピースをまとめて集めて部屋ごとに分けておきましょう。
ダイニングキッチンかリビングダイニングなのかによっても家具の配置が変わります。キッチンには、調理するのに必要なものから優先して置くようにすれば、最終的に食器戸棚がキッチンに入るか、リビングに置くことになるのか決まります。
最初に大型家具の場所を決める
大型家具は、ドアに近い壁に沿っておくと、ドアを開けた瞬間目の前に家具がそびえることもなく、視線の抜けがあれば部屋全体を広く見せることが可能です。
大型家具は、ここにしか置けないというような感じで収めることが多いのではないでしょうか。まずは大型家具の場所を決めてから他の家具を設置します。
リビングは家族揃ってくつろぎたい
テレビとテーブルやソファの位置関係が重要になります。テレビは窓から入る外の光を反射しないような場所に置くことがベストです。窓のすぐそばだと、車の音や外の物音で音声が聞き取りにくいことがあるので、少し窓から離して置いた方が良いかもしれません。
テレビをソファで見るのか、座卓で座って見るのか、ダイニングテーブルからも見られるようにしたいのか、みんなで相談して普段の生活をイメージして配置してみましょう。
迷ったら動線を書いてみる
朝から起きて一日の生活を想像して、自分だったらどう動くか、旦那さんだったらどのような動きをするか、お子さんだったら、と色分けして動きをなぞってみましょう。
線が重なり合い太くなったところは広くスペースを空けたいし、誰かがいると遠回りをして行くことになるのか、そこに行くまでに何通りかの方法があるかなど、書き込むことによって色々な問題点を発見することがあります。
寝室は安全を確保すること
地震の時、枕元に物が落ちてきたり倒れてきたりすることのないように、安全対策をしっかり行っておきましょう。寝室には背の高い倒れる危険性のある家具を置かないことがベストですが、住宅事情により置かざるを得ないなら耐震対策をしっかり行ってください。
置けない物は思い切って処分する
図面上であれこれ配置しても、どうしても置けない家具が出てしまったら、初めから無駄になるとわかっているものをわざわざ運ぶ必要はありません。引っ越し前に粗大ゴミに出すか、まだ使えそうなものならリサイクル業者に引き取ってもらうように手配しましょう。
配置図をドアや窓に貼っておく
これが一番大事なのです。このために今まで色々な作業を頑張って来たんです。転居先に荷物を運び入れてもらう際に、部屋ごとのドアや窓にその部屋の配置図を書いたものを貼っておきましょう。
家具の大まかな配置が分かれば大丈夫です。フリーハンドでも間取り図のコピーでも、ハッキリと大きく、誰が見てもわかるようにしておきましょう。これでめでたく「お客様―、これはどちらに置いたらよろしいですか?」とあちこちの部屋から声を掛けられることもなくなります。
まとめ
あらかじめレイアウトを決めておくことは、引っ越し作業をスムーズに進めるためにも大切ですが、実は引っ越し作業員のためだけではなく、自分たち家族のためでもあるのです。事前に練りに練って考えた家具の配置は、新しい家でも違和感なく生活しやすい空間になることでしょう。