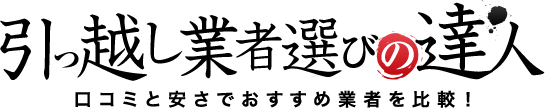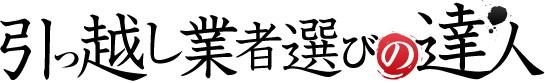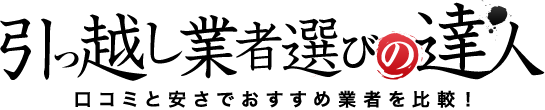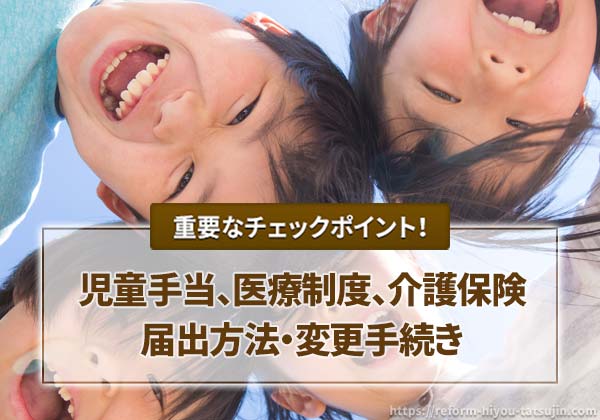
引っ越しは一人だけでも大変です。さらに子どもや同居の高齢者など家族の人数が多ければ、それだけ手続きも多くなります。基本的には、市区町村で手続きをして発行してもらったものは、転出する際には再び手続きをしなければなりません。
引っ越してから14日以内という期限があるので、転出と転入の届出のために役所に出向くときに、できれば一緒に済ませることをおすすめします。
引っ越しの際の児童手当の手続き
児童手当を受給している人が他の市区町村へ引越す場合は、転出届に記入した転出予定日に現在受給している児童手当の資格が消滅します。その後は、新しく住むことになった市区町村の役所で、新たに受給の申請が必要です。手続きは、両方の役所で行うことになります。
同じ市区町村内へ家族全員で引越す場合は、引っ越してから14日以内に転居届を提出することで新住所が登録されるため、特に手続きの必要はありません。
転出するときの手続きは
他の市区町村外に引っ越しをする場合は、引っ越しする月の分までは支給されますが、それ以降の分は、引っ越し先の役所での手続きが完了してから受け取ることになります。認定されるまでに時間がかかるので、一か月分空白期間ができないように速やかに手続きしましょう。
受給事由消滅届を提出する
自治体により名称が異なることがありますが、役所に備え付けの「児童手当の受給事由消滅届」もしくは「児童手当消滅届」に、必要事項を記入します。現住所や受給者名、転出予定日、転出先の住所と連絡先などを記載し、「市区町村外転出のため」などの理由を記入します。念のため認印も持参しましょう。
所得証明書を取得しておく
新しい住所地の役所では、児童手当を申請する際に、所得金額や扶養人数が記載されている「所得証明書」が必要になります。予め、現在の住所の役所で取得しておきましょう。引っ越しをする月により、前年度分、本年度分の両方が必要になることがあります。取得する際は、窓口で「児童手当認定のため」と伝えると良いでしょう。
転入するときの手続きは
新しい住所地の役所で「児童手当の認定請求書」をもらいます。請求者の氏名や住所、生年月日、児童の氏名、振込み希望口座などを記入し、シャチハタ以外の印鑑で捺印します。以下のものを持っていきましょう。
- 本人、もしくは代理人の顔写真つきの身分証明書
- シャチハタ以外の印鑑
- 受給者のマイナンバーがわかる通知カードか個人番号カード、またはマイナンバー記載のある住民票の写し
- 受給者名義の児童手当振込み希望口座の通帳かコピー
- 会社員は健康保険証かコピー、国民年金加入者は不要
- 必要年度の所得証明書
子どもと別居していたり、請求者が父母でなかったりする場合は、必要な書類が異なるので、担当窓口で問い合わせましょう。「認定請求書」は、自治体のホームページでダウンロードすることもできます。また、郵送でも受け付けている自治体もあります。必要な添付書類を確認し、不備がないようにしましょう。
医療制度の引っ越しの際の手続き
要介護や要支援の認定を受けている人の引っ越しでは、介護保険の手続きが、転出前と転出後、両方の役所で必要です。また、後期高齢者医療費被保険者証を所有している人は、引っ越し先によって若干手続きが異なります。
加入者本人や同じ世帯に住む家族以外の第三者が手続きをする際は、本人確認書類となる顔写真つきの身分証明書の提示と本人からの委任状が必要になります。
介護保険の手続き
要介護や要支援の認定を受けた人が、新住所地でも認定を引き継ぎ、スムーズな介護サービスを受けるための手続きです。
市区町村外の引っ越しの手続き
現在の住所地の高齢者福祉課などの介護保険担当窓口に「介護保険被保険者証」を返却するとともに介護保険の「資格喪失届」を提出し、「受給資格証明書」を発行してもらいます。自治体によっては、本人に直接手渡しせず、転居先の役所に送付するところもあります。
そして引っ越してから14日以内に、新住所地の担当窓口に「受給資格証明書」を提出し申請すると、今までと同じ介護度に認定されます。認定の有効期間は引っ越してから6か月間となります。介護サービスの利用などについては、担当者に相談すると良いでしょう。
同じ市区町村内での引っ越しの手続き
住所地の役所へ転居届を提出したあとに、介護保険担当窓口へ届け出ます。「介護保険被保険者証」を持っていきましょう。
後期高齢者医療費助成の手続き
生活保護受給者などを除く75歳以上の人と、65歳から74歳で一定の障害があり後期高齢者医療制度の認定を受けた人が、引越す際に必要な手続きです。
保険証にはそれぞれの都道府県の後期高齢者医療広域連合となっていますが、届出や申請などの業務は各市区町村の役所が担当しています。いずれも自治体により、新しい保険証をその場で受け取れる場合と、数日後に簡易書留郵便で送られる場合など、さまざまです。
都道府県外へ引っ越しするときの手続き
それまで住んでいた住所地の役所へ、カード型の「後期高齢者医療被保険者証」を返却します。すると、引っ越しする日まで使用できる保険証である「関係事項証明書」が発行されます。有効期限後は、各自でハサミを入れ、個人情報に気をつけ処分しましょう。
また、「負担区分証明書」を発行してもらいます。これが、引っ越し後の役所へ提出する書類になるので、なくさないように厳重に保管しておきましょう。このほか、被扶養者や障害認定、特定疾病認定を受けている人は、それらの認定証明書も発行してもらいます。以下のものが必要です。
- 保険証
- 本人、もしくは家族の顔写真つきの身分証明書
- シャチハタ以外の印鑑
都道府県外から引っ越してきたときの手続き
引っ越した先の住所地の役所で14日以内に手続きをします。以下のものが必要です。
- 本人、もしくは家族の顔写真つきの身分証明書
- シャチハタ以外の印鑑
- 引っ越し前の役所で発行してもらった「負担区分等証明書」
- 障害認定者は「身体障害者手帳」など
都道府県内の引っ越しで市区町村が変わるときの手続き
都道府県外へ引っ越しするときと同様、住んでいる住所地の役所へ保険証を返却し、引っ越しする日まで使用できる「関係事項証明書」を発行してもらいます。以下のものを持っていきましょう。
- 保険証
- 本人、もしくは家族の顔写真つきの身分証明書
- シャチハタ以外の印鑑
引っ越し後は14日以内に、引っ越し先の住所地の役所で新しい保険証を発行してもらいます。以下のものが必要です。
- 本人、もしくは家族の顔写真つきの身分証明書
- シャチハタ以外の印鑑
同じ市区町村内で引っ越しするときの手続き
同じ市区町村内の引っ越しの場合でも、14日以内に役所での手続きが必要です。引っ越し前の住所が記載されている保険証を返却し、新たに引っ越し後の住所が記載された保険証を発行してもらいます。以下のものを持って手続きに行きましょう。
- 保険証
- 本人、もしくは家族の顔写真つきの身分証明書
- シャチハタ以外の印鑑
引っ越し後は、慣れない土地での生活や引っ越し疲れなどで、体調を崩す人もいます。14日と余裕があるからそのうち手続きしようと思っていても、具合が悪くて動くに動けない状態になることも十分あり得ます。
そうした場合にすぐに医療機関にかかれるよう、早めの手続きをして新しい保険証を受け取っておくと安心です。また、児童手当は手続きが遅れると空白期間ができてしまい、その分はあとから請求することができません。子どもが多い家庭では特に遅れないように気をつけましょう。